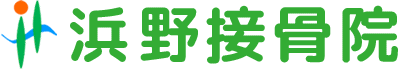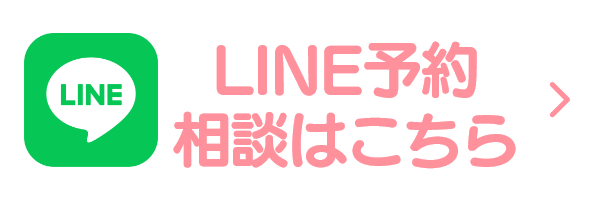呪いか、宝物か?──中学生に勧められて観た『君の膵臓をたべたい』感想
- 2025年07月03日
- カテゴリー:患者様との交流
※この記事には映画『君の膵臓をたべたい』のネタバレが含まれます。
静けさの中で心が満たされる物語
『君の膵臓をたべたい』は、住野よる氏による原作小説を映画化した作品で、タイトルのインパクトとは裏腹に、静かで繊細な感情の機微を描いた名作でした。

主演は、余命わずかの高校生・山内桜良(浜辺美波)と、彼女の秘密を偶然知ることになる「僕」こと志賀春樹(北村匠海/大人になった姿は小栗旬)。観る前は「青春映画」「ミーハー作品」といった印象を持っていましたが、実際に観終えた今は、そうした表面的な枠組みを越えて、胸に深く残るものがありました。
映画を観たきっかけ
この映画を観ることになったきっかけは、通院中の中学生の患者さんとの会話でした。以前から高評価なのは知っていたものの、どこか敬遠していた作品でもありました。普段の私が好んで観るジャンルはSFやサスペンス、壮大なストーリーの作品が多く、自分ではなかなかこのような作品を選ぶことはありません。
しかし、学生や女性といった、自分とは異なる感性を持つ人たちのおすすめに耳を傾けると、自分の中の「新鮮さ」や「忘れていた感覚」に出会えることがあります。映画とは、自分の人生では決して体験できない他人の人生を追体験することができる稀有なメディア。そして、その人生観や心の動きを少しでも共有・理解できたとき、自分の感性もまた少し広がるような気がするんです。
人はいつ死ぬかわからない
この作品が描く最大のテーマは、「人はいつ死ぬかわからない」という事実と、そこから導かれる「今をどう生きるか」でした。主人公・志賀春樹は、偶然見つけた『共病文庫』によって、クラスメイト・山内桜良が重い膵臓の病を患っていることを知ります。
彼女の命の期限を知りながら過ごす日々は、最初は戸惑いと気まずさを伴うものでしたが、やがてそれは、彼にとってかけがえのない時間へと変わっていきます。
特に衝撃だったのは、桜良の死が病気によるものではなく、通り魔事件という予期せぬ暴力によって訪れたことです。彼女が「死に向かって準備していた」のに対し、人生の幕はあまりにも唐突に、そして一方的に降ろされてしまった。その理不尽さが、「命の儚さ」というテーマをより際立たせていました。
つながることの幸福──『星の王子さま』
桜良は、孤独な人に寄り添うことができる特別な存在でした。一人ぼっちだった親友・恭子(大友花恋)に声をかけ、同じく孤独だった志賀春樹にも自然に近づいていきました。
彼女の存在が主人公の心を解かし、彼を少しずつ変えていく姿は、本作内でも随所に出てきた『星の王子さま』。この中の有名な一節に象徴されると思います。
「君がそのバラを特別に思うのは、君がそのバラに時間をかけたからなんだ」
まさに桜良と過ごした日々は、彼にとって“特別な時間”でした。誰かと深くつながること、誰かにとっての「たった一人」になること──それは恋愛感情を超えて、人が人として生きていく上で本質的に大切な営みなのだと、この作品は静かに語ってくれていたように思います。
そして何より、私自身が驚いたのは、自分でもその関係性に「あこがれ」のような感情を抱いてしまったことです。
恋愛というものは生物学的目的の過程であると、知識としても経験としても達観してる所がありました。
にもかかわらず、この映画のようなピュアな心の交流に心が動かされてしまった自分がいた。
これは不思議で、そしてちょっと笑ってしまうような、しかし否定しがたい「人間らしさ」の証でもあるように感じました。
「君の膵臓をたべたい」という言葉に込められた祈り
映画の中で象徴的に扱われるのが、タイトルにもなっているこの一言です。
物語の終盤、主人公がさくらへのメールに、たくさんの言葉を打ち込みましたがそれを全て消し、最後に送ったのはたった一言──「君の膵臓をたべたい」。
この言葉には、
「君と一つになりたい」
「君を生き続けさせたい」
「君を忘れたくない」
- という複雑な感情が込められていたように感じました。
それは、祈りのようであり、詩のようでもありました。
劇中でも桜良が「詩とは、願いや祈りだ」と語っていたことが思い出されます。
本棚の演出と心の変化
教師になった春樹が、自宅で『共病文庫』を手に取る場面があります。
その際、彼は本棚から『金閣寺』(三島由紀夫)と『蝿の王』(ウィリアム・ゴールディング)という2冊を少しどけて、その奥から共病文庫を取り出します。
『金閣寺』や『蝿の王』は、人間の内面の闇や孤独、破壊性を描いた文学作品です。対して、共病文庫は、桜良と過ごした日々の記録であり、人と人のつながりや祈りのような言葉が綴られたノートでした。

この演出は、まるで「かつての自分(孤独と破壊の象徴)から、新しい自分(他者と関わる温かさ)への移行」を示しているようでした。
「呪い」のような輝き
観終わったあとに思ったのは、あまりに美しく、儚く、強烈な初恋のような体験は、その後の人生の光と影の両方を決めてしまうということです。
強すぎる光は、ときにその後の人生に影を落とす。だからこそ、私はふと『北斗の拳』(私の中では愛のバイブル)の聖帝サウザーのセリフを思い出しました。

「こんなに悲しいのなら、こんなに苦しいのなら……愛などいらぬ!!」
このセリフが示すように、強烈な愛はときに“呪い”のようでもあります。けれど、主人公はその呪いを「宝物」として受け入れました。それが彼の人生を支える“核”になっていく──そんなラストだったように思います。
おわりに
この作品は、語りすぎることなく、静かに余白を残したまま、観る者に語りかけてきます。だからこそ、自分自身の感情が浮かび上がってくるのかもしれません。
自分で選んでいたら観なかったかもしれないこの作品に、思いがけず出会うことができた。感性の異なる誰かとの会話の中から生まれたこの出会い。これは単なる一作品の感想ではなく、私自身の“共病文庫”のような記録。そして宝物となりました。
Sさん、ありがとうございました^ ^